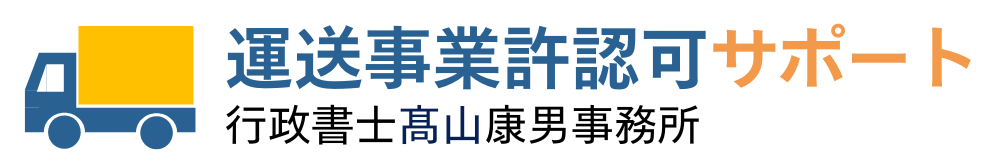一般貨物自動車運送事業許可申請
一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣(地方運輸局長)の許可が必要です。当事務所は運送業専門の行政書士として、これまで数多くの許可申請をサポートしてまいりました。複雑な要件の確認から書類作成、申請代行まで、開業に向けた全てのプロセスをワンストップでサポートいたします。
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業のことです。いわゆる「緑ナンバー」の事業用トラックで荷物を運ぶ事業を指します。
※ご注意:軽トラックで貨物運送を行う場合は「貨物軽自動車運送事業」となり、手続きが異なります。
許可取得のメリット
信頼性の向上
国の許可を受けた正規の運送事業者として、取引先や荷主からの信頼を得ることができます。
事業拡大
大手企業や官公庁との取引が可能になり、事業の幅を大きく広げることができます。
収益性の向上
白ナンバーと比べて運賃設定の自由度が高く、適正な対価で事業を行うことができます。
許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
1. 車両要件
最低車両台数
- 営業所ごとに5台以上の事業用自動車が必要
- 車両は使用権原があること(所有または1年以上のリース契約)
- 車検証上の用途が「貨物」であること
2. 営業所
営業所の要件
- 使用権原を有していること(所有または賃貸借契約)
- 建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないこと
- 規模が適切であり、事業計画を遂行するに足りる施設であること
3. 車庫(自動車車庫)
車庫の要件
- 原則として営業所に併設、または営業所から直線距離で2km以内
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保できること
- 計画車両の全てを収容できる広さがあること
- 使用権原を有していること
- 関係法令に抵触しないこと
4. 休憩・睡眠施設
休憩・睡眠施設の要件
- 原則として営業所または車庫に併設
- 運転者が有効に利用できる施設であること
- 使用権原を有していること
5. 運行管理体制
運行管理の要件
- 営業所ごとに、車両数に応じた運行管理者を選任すること
- 運行管理者は運行管理者資格者証を有する者
- 運行管理者は他の営業所の運行管理者との兼任不可
- 点呼、運転者の指導監督等が確実に実施できる体制であること
6. 整備管理体制
整備管理の要件
- 営業所ごとに、車両数に応じた整備管理者を選任すること
- 整備管理者は実務経験または自動車整備士資格を有する者
- 定期点検、日常点検が確実に実施できる体制であること
7. 資金計画
所要資金と資金調達
- 所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的かつ確実であること
- 所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日以降常時確保すること
- 自己資金は申請日の直前の決算期(個人は申請日)において、残高証明書等で確認できること
重要:自己資金の確認は非常に厳格です。申請時点で、事業開始に必要な資金を確実に保有していることが求められます。
8. 法令遵守
欠格事由に該当しないこと
- 申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当しないこと
- 貨物自動車運送事業の許可取消しから5年を経過していること
- 申請前5年間に自動車運送事業に関し不正な行為をしていないこと
- 社会保険等に適正に加入すること
申請から許可取得までの流れ
STEP 1:ご相談・要件確認
まずは無料相談にて、事業計画や許可要件の充足状況を確認いたします。要件を満たしていない場合は、対応策をご提案いたします。
STEP 2:ご契約・書類準備
ご契約後、申請に必要な書類の収集と作成に着手いたします。お客様には必要最小限の書類をご準備いただくだけで結構です。
STEP 3:申請書類の作成
複雑な申請書類一式を当事務所が作成いたします。営業所や車庫の図面作成、所要資金の算出なども全てお任せください。
STEP 4:運輸支局への申請
管轄の地方運輸局(運輸支局)へ申請書類を提出いたします。申請手数料は12万円です。
STEP 5:審査期間(約3〜4ヶ月)
運輸局による書面審査が行われます。必要に応じて補正対応や追加資料の提出を行います。
STEP 6:許可通知
審査を通過すると、許可証が交付されます。ただし、この時点ではまだ事業を開始できません。
STEP 7:許可後の手続き
登録免許税の納付(12万円)、運行管理者・整備管理者の選任届、社会保険等の加入、運賃料金の設定届などの手続きを行います。
STEP 8:運輸開始届・事業開始
車両の登録(緑ナンバーの取得)を行い、運輸開始届を提出することで、ようやく事業を開始できます。許可から1年以内に事業を開始する必要があります。
必要な費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税(許可後) | 120,000円 |
| 行政書士報酬 | 別途お見積り(ご相談ください) |
当事務所のサポート内容
運送業専門の行政書士として、以下のサポートを提供いたします。
要件診断
現在の状況で許可要件を満たしているか、詳細に診断いたします。
書類作成代行
申請書、事業計画書、添付書類など、必要な書類を全て作成いたします。
申請代行
運輸局への申請手続きを代行し、スムーズな審査を実現します。
補正対応
審査中の補正指示にも迅速に対応いたします。
許可後手続き
運行管理者・整備管理者の選任届など、許可後の手続きもサポートします。
よくあるご質問
Q. 許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
申請から許可までは通常3〜4ヶ月程度かかります。ただし、書類の準備期間を含めると、ご相談から事業開始まで5〜6ヶ月程度を見込んでおく必要があります。
Q. 個人でも許可は取得できますか?
はい、個人事業主でも取得可能です。ただし、法人に比べて信用面で不利になることもあるため、将来的に法人化を検討されることをお勧めします。
Q. 自己資金はいくら必要ですか?
車両台数や営業所の規模によりますが、一般的には少なくとも1,000万円〜1,500万円程度の自己資金が必要です。詳細な資金計画については、無料相談にてご説明いたします。
Q. 運行管理者資格を持っていませんが、許可は取れますか?
運行管理者資格は許可取得後の選任までに取得すれば問題ありません。ただし、申請時点では、誰が運行管理者になるのか明確にしておく必要があります。
まずは無料相談から始めませんか?
一般貨物自動車運送事業の許可取得は複雑ですが、運送業専門の当事務所が全面的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。