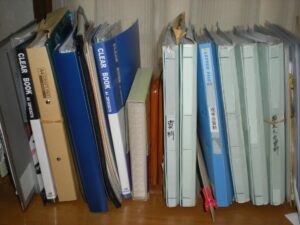事故報告、事故記録と保存、運転者台帳、車両台帳、事業計画書・実績報告書の提出それぞれ義務担っています。巡回指導で見られるのは、事故の内容ではなく報告、記録、保管が期日までに適正にされているかです。他の台帳、報告書も同様です。つまり、帳票の整備と報告がされているかです。
法令の確認:事故発生時における報告義務・記録保存の義務
貨物運送事業者は事業用自動車に事故があった場合はその事故の重大さによって報告・記録・保存の義務が異なります。。
事故の重大さにより「事故の記録」「事故報告書の提出」「事故速報」と義務が増していきます。
貨物自動車運送事業者が知っておくべき事故対応義務
巡回指導でよく指摘される「事故記録の作成と保存義務」について、法的なルールを解説します。事故発生時に適切な対応ができるよう、事前に確認しておきましょう。
1. 交通事故発生時の記録保存義務
人の死傷若しくは物損、または自動車事故規則第2条に規定する事故の場合、事故記録の作成と3年間の保存が義務づけられています。
記録対象となる事故
- 人身事故(死傷事故)
- 物損事故
- 自動車事故報告規則第2条に該当する事故
記録しなければならない内容
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 関係者情報 | 乗務員の氏名 事故の当事者(乗務員を除く)の氏名 |
| 車両情報 | 車両の登録番号等 |
| 事故詳細 | 事故の発生日時 事故の発生場所 事故の概要(損害の程度を含む) |
| 分析対策 | 事故の原因 再発防止対策 |
事故発生後3年間、営業所において保存することが義務付けられています。(国土交通省道路局)
2. 重大事故発生時の報告義務(30日以内)
報告対象となる重大事故
- 自動車の転覆、転落、火災、鉄道車両との衝突・接触
- 10台以上の車両の衝突・接触
- 死者または重傷者の発生
- 10人以上の負傷者の発生
- 積載物(危険物・火薬類・高圧ガスなど)の飛散・漏洩
- コンテナの落下
- 酒気帯び運転、無免許運転、大型車無資格運転、麻薬等運転を伴う事故
- 運転者の疾病により運転継続が不可能となった場合
- 救護義務違反があった場合
- 車両の装置の故障により運行不能となった場合
- 車輪の脱落、被牽引車の分離(故障によるもの)
- 鉄道施設の損傷により3時間以上運転休止させた場合
- 高速道路等で3時間以上通行禁止となった場合
- 国土交通大臣の指示によるもの
3. 特定の重大事故発生時の速報義務(24時間以内)
速報が必要な特定重大事故
- 2人以上の死者が発生した事故
- 5人以上の重傷者が発生した事故
- 10人以上の負傷者が発生した事故
- 積載物の飛散・漏洩を伴う事故
- 酒気帯び運転を伴う事故
- その他、国土交通大臣が特に指示した事故
速報の提出期限と方法
事故発生から24時間以内に、電話、FAX、メール等で運輸支局長または運輸監理部長に速報することが義務付けられています。
※本記事の内容は法令改正により変更される場合があります。最新の法令や通達をご確認ください。
※ご不明な点は当事務所までお気軽にご相談ください。
巡回指導対策
巡回指導では事故の大きさではなく、記録が適正に記入されており保存されているかを確認されます。
1.事故記録が適正に保管され、保存されているか。
⑴事故記録簿を備え付けているか
事故がない場合でも、事故記録簿として一覧表やチェックリストと共にファイルにして保管しておくといいでしょう。
⑵適正に記録され、保存されているか
事故記録に記載する8項目は確実に記載する。
事故発生時に記入はしているが、その後に事故の原因、再発防止策が漏れていることがあるので注意。
2.自動車事故報告書を提出しているか
24時間以内(速報)、30日以内(重大事故)に支局へ報告しているかの確認です。
緊急事態マニュアルを作成し、どのような場合に速報や報告が必要になるのかをマニュアルに記載し報告漏れが無いよう体制を整備しておくと良いでしょう。
ポイント!
安全会議の義務は?
貨物自動車運送事業において、「毎月1回の安全会議」の開催自体は法律上の義務ではありません。ただし、運送事業者には運転者への指導教育義務が課されており、事故発生時にはその原因分析と再発防止策を講じ、他の乗務員にも適切に共有・指導することが求められます。そのため、月に一度、及び事故発生時には安全会議として定期的に指導教育を行い、事故やヒヤリ・ハット事例を共有する機会を設けることは、実務上非常に重要です。義務ではないとはいえ、事故防止と安全管理体制の強化のためには、継続的な開催が望まれます。