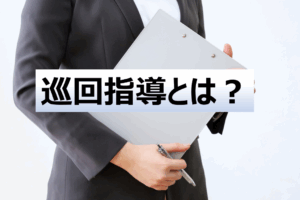2024年4月1日から、自動車運転者の労働時間等に関する規制が大きく変わりました。いわゆる「2024年問題」として、運輸・物流業界では対応が急務となっています。この「2024年問題」と深く関わるのが「改善基準告示」です。
しかし、「労働基準法」と「改善基準告示」、そして「2024年問題」という言葉が入り混じり、その関係性や違いが分かりにくいと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、行政書士の視点から、これらの関係性と違いを明確に解説いたします。
1. 労働基準法とは?
「労働基準法」は、日本の労働条件に関する基本的な法律です。賃金、労働時間、休日、安全衛生など、すべての業種の労働者に共通する最低基準を定めています。
この労働基準法において、時間外労働には上限規制が設けられています。原則として、月45時間・年360時間が上限となります。
2. 2024年問題とは?
「2024年問題」とは、2019年4月に改正された労働基準法によって、自動車運転者(トラック、バス、タクシー)の時間外労働の上限規制が、2024年4月1日から他の業種と同様に適用されることを指します。
これまで、自動車運転者の労働時間については、労働基準法の一部規定が適用除外とされ、代わりに「改善基準告示」という特別な基準が設けられていました。しかし、働き方改革の一環として、自動車運転者にも時間外労働の上限規制が適用されることになったのです。
つまり、2024年問題の本質は、労働基準法による時間外労働の上限規制が、自動車運転者にも適用開始されることにあります。
3. 改善基準告示とは?
一方、「改善基準告示」は、自動車運転者の労働時間、休息時間、運転時間などについて、具体的な基準を定めた厚生労働省の告示です。労働基準法を補完し、自動車運転者の特殊な労働環境を踏まえたより詳細なルールを定めています。
改善基準告示は、2024年4月1日にも改正が行われ、時間外労働の上限規制の適用に合わせて、拘束時間や運転時間などの基準が見直されました。
4. 2024年問題と改善基準告示の関係・違い
2024年4月 労働基準法の主な改正内容(トラック事業)
2024年4月1日をもって、トラック運転者の時間外労働について、以下の時間外労働の上限が適用されています。猶予期間は終了しました。
- 時間外労働の上限:
- 原則: 月45時間・年360時間
- 例外(労使協定(36協定)を締結した場合):
- 年間の上限: 960時間
- 複数月の平均: 月80時間以内(休日労働を含む)
- 単月の上限: 100時間未満(休日労働を含む)
- 連続する2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の平均: 各々80時間以内(休日労働を含む)
重要なポイント:
- 改善基準告示にある「拘束時間」ではなく「時間外労働」に上限が設けられた点に注意が必要です。
- 上記の上限は、休日労働の時間を含みます。
- 猶予期間は終了し、上記の上限が適用されています。
36協定締結後の規定
時間外労働を上記の原則上限を超えて行う必要がある場合、事業者は労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で、**36協定(時間外・休日労働に関する協定)**を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定を締結した場合でも、上記で示した例外の時間外労働の上限が適用されます。
- 36協定には、時間外労働・休日労働の必要性、具体的な業務の種類、時間数、対象となる労働者の範囲などを明確に定める必要があります。
- 特別条項付きの36協定を締結する場合でも、年間の時間外労働時間の上限は960時間となり、複数月の平均や単月の上限、連続する複数月の平均についても厳格な制限が設けられています。
- 36協定は、労働者の健康確保に最大限配慮した内容とする必要があります。
まとめ
2024年4月、トラック運送事業における労働基準法の猶予期間が終了し、時間外労働の上限規制が本格的に適用されています。事業者の皆様は、この法改正の内容を改めて十分に理解し、36協定の適切な締結・運用を行うとともに、労働時間管理体制の見直しや業務効率化をより一層進める必要があります。